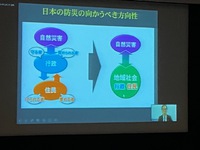一般質問(個人)で登壇しました。
2022年03月11日
鈴木洋一 at 11:53 | 活動
長野市議会は、現在、令和4年3月定例会が会期中ですが、去る3月4日(金)、一般質問で登壇し、荻原市長はじめ理事者と議論いたしました。その内容をご紹介します。今回取り上げた事項は、①新型コロナウイルス感染症対策、②信濃川水系河川整備計画と治水対策、③市指定文化財である旧作新学校本館改修整備、④川中島古戦場史跡公園整備、についてです。
①新型コロナ関係
鈴木:長野市の感染の拡大防止に係る対策について、専門的知識及び意見を反映させることを目的として、新たに「長野市新型コロナウイルス感染症有識者会議」を設け、昨年12月22日以降3回の会議を開催しておりますが、改めて有識者会議の位置づけのほか、幾つかお伺いをいたします。
長野市における新型コロナウイルス感染状況は、1月8日以降急激な感染拡大期に入り、1月13日には県の感染警戒レベルが5に引上げられ、翌14日、長野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、長野市新型コロナウイルス感染症対応方針の改定と市長メッセージが発出されました。
しかし、こういうときにこそ有識者会議を開催し、市としての対応方針や市長メッセージに生かすべきではないでしょうか。市長が公約で掲げた(仮称)感染症対策調査チームは、保健所内に構成するとしていたことから、私なりに政府の基本的対処方針分科会や、厚労省アドバイザリーボードといったような感染症や医療の専門家から、基本的な感染拡大防止対策や、本市の現状を踏まえた具体的な提言を求めたかったのではないか、と受け止めました。国や県の対応方針を基本としつつ、感染状況の情報収集と解析により、長野市独自の対応方針を導き出すための有識者会議であるべきではないか、と考えます。
ぜひ、有識者会議を明確に位置づけ、形式的な会議に終わらせることがないよう強く求めたいと思います。
そこで、基本的なことをお聞きしますが、長野市は有識者会議をどう位置づけているのか。また、有識者会議との関係において、対応方針の改定手続は適切だったのか、伺います。
市長:まず、有識者会議の位置づけでありますが、本市の感染状況等を踏まえまして、私が本部長である「長野市新型コロナウイルス感染症対策本部」に対して、保健、医療、経済活動などの専門的知見からアドバイスをいただくという会議です。
特に、4月からの善光寺御開帳期間中に、様々なイベントが開催され、多くの参拝客や観光客などが長野市にお越しになりますので、関連する催事が安心安全に開催されるために、主催者が作成し、県に提出いたします感染防止安全計画等に対しても、御意見をいただいている、ということでございます。これまでに3回の会議を開催し、有益な御助言を頂戴してまいりました。
続きまして、市の対応方針の改定手続についてですが、国の基本的対処方針や県の対応方針の見直し、あるいは県において感染警戒レベル変更などが行われた際に、本市の取組の全体的な方針について、対策本部において改定を決定しているものでございまして、適時適切に改定しております。
有識者会議設置後は、市の対応方針に対して、有識者会議から御意見をいただき、必要があれば改定を行うこととしております。 以上です。
鈴木:私も、3回傍聴させていただいている中での印象ですが、やはりどことなく説明の場、そうした会議となっているのではなか、と受け止めております。この有識者会議の設置目的に、感染拡大防止策、先ほどの、例えば御開帳等の対応も当然必要だけれども、やはり肝腎の感染拡大防止についての議論はやや少ないのではないか、と感じておりますので、その辺は指摘をさせていただいて、次回、今月行われるかと思いますが、そちらのほうにしっかりと反映をしていただきたいと要望させていただきます。
本年1月の市内における感染急増の背景には、同居家族の感染者数の増大がありました。
1月下旬、家庭内感染により陽性者となった私の知人の事例では、保育園に通うお子さんのクラスで、園児数名が発熱により園を休み、その後、当該クラス全ての園児が濃厚接触者となり、検査の結果、知人のお子さん、続けて、私の知人夫婦も陽性となりました。
詳細は割愛しますが、知人夫婦が濃厚接触者との判定がなされるまでの数日間、通常通りの生活を送ることが可能であったとのことであります。陽性となったお子さん、小さなお子さんがいる家庭では、保護者等の家族はお子さんとの接触は避けられず、罹患するリスクは極めて高く、さらに無症状がゆえに、市中感染を拡大させる可能性をも高めます。
以上のことから、集団生活を送る施設等における感染拡大防止について伺います。
保育園のような集団生活を送る施設内において、1人でも発熱等の感染が疑われる症状が発生した場合、すぐにPCR検査を受けてもらうなど、感染拡大防止に迅速に取り組むことが求められます。
保健所は、保育園等の施設との間で、各施設が利用者の体調管理等、確認すべき事項について整理し共有できているのでしょうか。また、パンデミックの際、それぞれの施設内で窓口となる責任者を明確にし、保健所と情報や対応策等について、迅速に共有を図れるような仕組みを構築することが必要ではないでしょうか。
さらに保健所は、保育園や保護者に対し、保健所や医療機関での迅速な検査につなげるなどの支援体制を整えているのでしょうか。
保健所長:施設の利用者の体調管理などの、確認すべき事項の整理と共有についてですが、保健所では第1波の感染拡大を受けて、令和2年の7月と9月に、学校、保育所、高齢者障害者等の施設向けの研修会を延べ9回開催いたしまして、参加いただきました500名の方に対しまして、利用者及び従事者の健康確認、感染予防の基本、感染者が発生したときの具体的な対応等を説明し、施設内での徹底を依頼しました。
また、この研修会で使用したマニュアルは、県と合同で作成したものでありますが、市保健所のホームページにも掲載をいたしまして、各施設で利用できるよう、広く周知をしております。
次に、施設の窓口の明確化と迅速な情報共有の仕組みについてですが、施設で感染者が発生した場合には、私どもが直接、または所管部署を通じて、直ちに当該施設に連絡をいたしまして、感染者の発生状況や感染対策の状況などを把握するとともに、必要に応じまして現地に赴いて、さらに情報収集や具体的な対策の助言などを行っておりまして、迅速な情報共有を図っているところであります。
次に、保育園や保護者に対する迅速な検査につなげる等の支援体制についてですが、保健所では感染が判明した当日、または翌日には感染者と施設に対して詳しい聞き取りを行いまして、濃厚接触者を特定するとともに、検査の適切な時期であります、感染が考えられます3日から5日後に検査を実施し、また既に症状がある方については、速やかに医療機関を受診し、検査を受けるよう指導しております。
鈴木:先ほども御紹介したとおり、例えば発熱の症状があるような場合というのが、今回のオミクロン株の特性等を考えてみると非常に重要だと思います。例えば、施設の中で検査は陽性かどうか、オミクロンかどうか、コロナかどうかは分からないが、そういった症状があった場合に保健所といろいろなコミュニケーションがとれるような仕組み、そうした体制が、例えば、これからBA.2とかいろいろ言われていますが、必要じゃないか、と思いますが、いかがでしょうか。
保健所長:保育所等において、利用者または広く従事者も含めてですが、何らかの症状が見られた場合には、市内にあります診療検査医療機関を速やかに受診をしていただくことが肝要であります。保健所への連絡を通してからの受診ではなくて、まず症状があったら受診、このことはしっかり徹底をしていきたいと思っております。その上で、新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、医師から届出が来ますので、その
上でしっかり施設や、御本人方の情報収集を行って対応していくことになっています。
鈴木:今の部分、徹底よろしくお願いいたします。同居家族のうち1人でも濃厚接触者となった段階で、同居する全ての家族に対し、検査結果が判明するまでの間、ウイルスの特性に応じた対応策を講じる必要があるのではないでしょうか。
例えば、施設内で複数人の感染が疑われる場合、施設に通う人はもちろん、その同居家族に対し、行政として行動自粛等を強くお願いするべきではないでしょうか。
保健所長:濃厚接触者の同居している家族等への対策について、濃厚接触者がいらっしゃって、確かに感染の可能性はありますが、その方が発症もしていない、また、まだ検査で感染も判明していない段階において、その方が必ず感染しているとまでは言えませんので、行動自粛といった強い要請を行政から一方的に行うことはやはり適切ではないと考えております。
しかしながら、感染の可能性があることは事実でありますので、保健所では、濃厚接触者であることが判明した時点で、同居の方との生活空間をしっかり分け、マスクの着用と手指消毒、物品の消毒などの感染防止対策を徹底するように指導しておりまして、濃厚接触者が仮にお子さんのような場合でありますと、こういった対応が困難なことが予想されますので、そういった場合には、濃厚接触者の検査の結果が出るまでは、外出を控えていただくようお伝えをしてございます。引き続き、個々の状況を踏まえて、適切に対応し、感染拡大防止に努めてまいりたいと思っております。
鈴木:こちらのほうも、重ねてお願いをしたいと思います。昨年3月の定例会代表質問において、救急搬送先の決定困難事例について取上げましたが、報道によりますと、新型コロナウイルス感染が第6波に入った今年の1月下旬、長野市消防局管内で救急搬送困難事例が3件あり、特に1月25日の市内の90代女性の場合、医療機関に受入れを6回照会し、搬送開始までに1時間2分かかったとのことであります。
1月下旬の市内における救急搬送困難事案について、市消防局警防課は、現時点で都市部のように救急搬送体制が逼迫した状況ではない、また、医療機関の病床逼迫が原因かどうか判断できない、との見解を示されていました。
2月8日時点の、県全体の確保病床使用率は44.4%でしたが、北信ブロックにおける確保病床使用率は71.9%であったことから、1月下旬には病床逼迫の影響が出ていたのではないか、と推察しますが、医師の判断により、入院措置が必要とされた新型コロナウイルス感染者を確実に入院できていたのか、また、なぜ搬送開始まで1時間以上かかったのか、その原因は何だったのか、改善が図られたのか。
保健所:私から、入院が必要な感染者の入院の状況についてお答えいたします。本市の入院患者が最も多かった1月30日において、長野医療圏と北信医療圏を合わせたいわゆる北信ブロックでありますけれども、病床確保数128床に対して104人が入院しておりまして、病床使用率81.3%でありました。この数字から、病床に決して余裕があるとまでは言いませんけれども、入院が必要とされる感染者の入院病床は、これまでのところ確保されていると考えております。
消防局長:私からは、困難事案につきましてお答えをいたします。最初に、消防局管内における国の基準に基づく搬送困難事案の状況でございますが、本年1月1日から2月末日までの間に3件の事案がございまして、前年同期との比較では、1件のマイナスという状況でございます。
また、総務省消防庁が公表してございます全国52消防本部の中では、2月20日の時点で5番目に少ない状況となっております。
御質問の事案でございますが、119番通報により出動した救急隊は、一般の傷病者として、医療機関へ受入れの問合せを開始したところ、他の救急事案に対応中で、処置困難との理由から受入れに至らず、照会が3回に及んだこと、また、症状などを確認する中で、新型コロナウイルス感染症が疑われたことから、医療機関との照会に3回を要したこと、その結果、医療機関への照会回数が6回となり、搬送開始までに1時間を要したものでございました。
後日、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の救急搬送の件につきましては、保健所と医療機関において改めて確認をいただきまして、2月に入ってから、同様のケースの救急搬送におきましては、全てスムーズな受入れがなされてございます。
なお、本年2月末日までの救急出動3,339件のうち、約99%は救急隊からの照会が2回以内で搬送先が決定している状況でございまして、救急搬送業務におきましては、各医療機関には円滑な対応をいただいているものと考えてございます。以上でございます。
鈴木:ありがとうございました。 しっかりと対応を引き続きお願いしたいと思います。オミクロンの急増期であった冬季は、脳出血、心筋梗塞などの患者が多い時期でもあり、一般の救急が滞れば手後れとなる患者の続出が懸念されます。
オミクロン株は従来株に比べて重症化しにくいと言われていますが、感染爆発による医療逼迫をいかに回避するかが一番の課題であることから、宿泊療養と自宅療養を含めた医療全体のリソースを確保するために、自宅療養の在り方が重要だと考えます。
保健所が自宅療養者に対し、電話での健康観察を行い、仮に容体が悪化した場合、かかりつけ医、輪番医への診療を依頼されているとのことですが、迅速な対応が取れているのでしょうか。具体的な手順はどのような内容となっているのでしょうか。
また、かかりつけのクリニックや薬局を含めた地域の関係機関全体で、自宅療養者に医療行為を提供できる体制の構築が急務ではないかと考えますが。
保健所長:自宅療養者の容体が悪化した場合の対応についてですが、第6波で自宅療養者が700人を超える日もありましたけれども、保健所による毎日の健康観察や、感染者の方からの御相談において症状の悪化が認められる場合には、かかりつけ医など診療可能な医療機関に保健所から連絡をして、薬の処方等をしていただくとともに、症状の悪化が著しい場合や夜間等でかかりつけ医などの対応が難しい場合には、私どもが連絡を受けた上で、長野医療圏で定めております輪番の病院に診療や入院をお願いし、また救急搬送が必要な場合には、保健所から救急隊の要請を行うなど、自宅療養者への迅速な医療の提供に努めているところであります。
なお、こうした対応については、24時間対応をしているところでございます。
次に、自宅療養者へ医療行為を提供する体制についてですが、第6波の感染急拡大に対応するため、医師会の御協力をいただきまして、2月1日、市内の医療機関を対象に、症状が悪化した自宅療養者に対する診療や処方が可能かどうかなどを調査したところ、かかりつけ医の患者であれば可能とした医療機関51か所、初診の患者でも可能としたところが33か所、抗ウイルス薬の治療も可能41か所などとなっておりまして、改めて、こうした医療機関、また関連する薬局の活用を図ることによりまして、自宅療養者への医療の提供の確保を図っているところであります。
鈴木:長野県において、1月27日から3月6日までまん延防止等重点措置が適用され、市は国や県の方針に基づき、新型コロナウイルス感染症対応方針の改定や、市長メッセージの発出等の取組が行われてきましたが、顕著な効果があったと考えていいのでしょうか。
例えば、定点観測により、本市の人流抑制や、人数制限等の実態がどう推移したのか数値で把握するとともに、市の対応方針、市長メッセージの内容や発出方法などについて、有識者会議の意見等も聞きながら、幅広い観点から分析評価し、今後の取組に生かしていくべきではないでしょうか。
市長:令和2年5月以降、市の対応方針や市長メッセージは、感染警戒レベルが高くなった際などに発信し、動画をホームページへ掲載しております。その効果についての御質問ですが、国、県の取組を踏まえて、本市としての全体的な取組の方向性を示すことや、私が直接市民の皆様へ呼びかけることにより、市の対策や姿勢を発信するという役割を果たしているというふうに考えてございます。
また、発信した情報により、市民の皆さん、事業者の皆様が感染予防を徹底していただく一つのきっかけになったと思っています。なお、その効果が顕著であったかにつきましては、判断基準については持ち合わせておりません。
次に、人流抑制や人数制限の推移についてですが、これらは基本的に特措法に基づく県知事の要請でありまして、市としては推移の把握は行っておりません。市対応方針の内容や市長メッセージ等については、市の対策を取りまとめて、市民の皆さん、事業者の皆様に御協力をお願いするための情報発信であり、感染状況に応じて見直していることから、今後も有識者会議からの御意見も生かしながら、適時適切に改定してまいります。
新型コロナウイルス感染症対策については、国、県、市の役割分担の中で、皆様の御理解と御協力をいただきながら、本市として最大限の取組を実行してまいります。
②信濃川水系河川整備と治水対策について
鈴木:いろいろ御腐心続いておられるかと思います。これまでの取組には敬意と感謝を申し上げさせていただきつつ、これからもよろしくお願いをしたいと思います。
次に、信濃川水系河川整備計画変更骨子案と治水対策について伺います。
信濃川水系河川整備計画変更骨子案が策定され、改訂に向けた検討が進められています。そもそも千曲川犀川を含む信濃川水系の河川整備は、平成20年6月に策定された信濃川水系河川整備基本方針で、立ヶ花及び杭瀬下地点における計画高水流量を毎秒9,000立方メートル、5,500立方メートルと定め、それとは別におおむね30年かけて具体的な工事を行うため、平成26年1月に策定された信濃川水系河川整備計画では2か所の河道配分流量を、基本方針の計画高水流量を大きく下回る毎秒7,300立方メートル、4,000立方メートルとしていました。
そして整備途上にあった令和元年に台風第19号災害が発生し、そのときの流量は2か所とも整備計画の河道配分流量を大幅に上回り、さらには基本方針が定めた計画高水流量を杭瀬下では大幅に上回り、立ヶ花についても設定値に迫る勢いだったのであります。
台風第19号の洪水を受け、現在、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトに基づく整備が進められていますが、整備計画を改訂し、プロジェクトとの整合性を図ることが必要であると理解しています。
そこで骨子案を見ますと、基準地点である立ヶ花の河道配分流量、毎秒8,300立方メートルへの改定は、台風第19号時の流量である毎秒8、387立方メートルの近似値ですが、長野市の上流に位置する杭瀬下地点における河道配分流量を、毎秒4,900立方メートルとしていることには理解が及びません。
台風第19号時における杭瀬下地点の流量は、残念ながら国は定められている観測ができなかったとしていますが、杭瀬下上流の観測地点である生田での流量を毎秒7,267立方メートルとしていることから、理論的には杭瀬下地点での流量はそれ以上とみられます。
仮に、生田の7,267立方メートルがそのまま流下したとしても、信濃川水系河川整備計画変更骨子案で提示している杭瀬下地点の河道配分流量、毎秒4,900立方メートルを2,367立方メートル上回る流量となり、杭瀬下の下流域である篠ノ井から若穂に至る流域住民には到底、受け入れがたいものであります。
これまでの整備計画は限られた諸条件の基で、整備の実現性を優先に策定されたものだと推察しますが、今回は台風第19号での大災害を受けたのであり、将来にわたり住民の生命と財産を守り切る立場から、現実に起こった値、つまり実績値を基本に河川整備計画の河道配分流量を検討すべきであります。
長野市は骨子案にある杭瀬下地点の河道配分流量をいかに受け止めているのか、また台風第19号時の杭瀬下地点での実績値を基本とした河道配分流量へと見直しを強く求めるべきではないか。さらに上流の杭瀬下が定まれば、立ヶ花の毎秒8,300立方メートルを再考する必要があると考えますが。
建設部長:信濃川水系緊急治水対策プロジェクトでは、令和元年東日本台風災害の洪水実績に対し、令和9年度までの、令和元年洪水における千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水被害を防止することとしております。
現在、手続を進めている信濃川水系河川整備計画の目標原案においては、さらなる治水安全度向上のため、基準地点である立ヶ花においては、戦後最大を更新した令和元年10月洪水と同規模の毎秒9,400立方メートルを目標流量とし、河道配分流量を毎秒8,300立方メートルとして堤防の決壊、越水等による家屋の浸水被害の防止または軽減を図ることとしております。
議員御質問の内容について、国土交通省、北陸地方整備局、千曲川河川事務所に問い合わせたところ、杭瀬下地点の河道配分流量を毎秒4,000立方メートルから4,900立方メートルに引き上げたことについては、令和元年10月洪水規模に対し、信濃川水系河川整備基本方針で最終目標である計画高水流量5,500立方メートルに向け、基準地点立ヶ花をはじめ、下流域を含めた上下流バランスを考慮した上で設定された流量であるとのことでありました。
変更原案で示されている内容のうち、上流のダムや新設される遊水地などの洪水調節施設による調節流量が立ヶ花地点においては毎秒1,100立方メートルとされております。そのうち、流域治水という観点から、流域自治体が一定量の調節量を担うことから、事を国から求められていることもあり、市では具体的な取組を推進するため、国の考えを確認している状況です。
現在、国では河川整備計画変更原案に対する住民意見募集を開始しており、その後に市を含めた関係機関協議が行われる予定です。市では自治体における流域治水上の調節量に加え、議員御質問の河道配分流量の見直しの点についても、その数値の妥当性について確認してまいりたいと考えております。
鈴木:今、御答弁あったとおり、この妥当性、非常に大事だと思っております。例えば、先ほど1,100立方メートルですか、この具体的な数値をあてがっていかないと、4,900、これは大丈夫なんですかと。基本方針だって5,500ですよ。5,500に対して7,000トンを超える流量が流れてきたという事実をしっかりと受け止めて、長野市のほうとしても、また調査していただいて、必要な要望はしていっていただきたいということを求めたいと思います。
市長は昨年の選挙公約で、これまで培ってきた人とのつながりを生かし、国や県への働きかけを強め、東日本台風災害へのさらなる支援を強力に要望していくと掲げられました。そのためにはまず台風第19号の際、杭瀬下の下流域の篠ノ井から若穂に至る間において、越流、浸水と甚大な被害が発生したことを踏まえ、長野市南部の安全性についてもっとも重要な数値である立ヶ花と杭瀬下地点の河道配分流量の実績値を基本に改訂するよう強く働きかけ、台風災害で甚大な被害を受けた自治体のリーダーとして、災害に強いまちづくりに向け、全力で取り組んでいただくことを期待しますがいかがでしょうか。
また、市長は施政方針の中で、緊急対策の1つとして防災復興を取り上げ、(仮称)治水対策研究会を設置と防災・減災を強化するとしています。昨年12月定例会で布目議員への答弁で、千曲川関係5団体での合同要望活動をバージョンアップさせる形で取り組むとしていますが、やや不十分かなと受け止めております。大事なことは今までの延長線ではなく、流域住民のリスクや不安などの切実な声、要望等を受け止め、市と一体となった取組としなければならないと考えますが。
市長:信濃川水系河川整備計画の変更の手続につきましては、国において河川法に基づき、進められているものと考えております。先に示されました変更原案では、河川整備基本方針で定めた目標に向けて、過去の洪水における洪水特性や現在の河川整備状況、上下流、本支川の整備バランスとを総合的に勘案し、段階的かつ着実な河川整備を実施することで、戦後最大規模の洪水に対し、災害発生の防止または軽減を図る
とされております。杭瀬下地点の河道配分流量についても、その考えに基づき適切に設定されていると理解しております。
令和4年中に予定されております関係機関との協議などを通じて、その数値について改めて確認するとともに、仮に疑義が生じているような部分があれば、私がしっかり意見を申し立ててまいりたいと思っています。
また、今回の計画変更により、河川整備計画に位置付けられる信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおける流水域整備、河道掘削等の河川における対策が確実に実施されることで、長野市南部を含めました市全域における治水安全度が向上することから、本年1月にはオンラインにより、国土交通大臣政務官に整備計画の前倒しの要望を行いました。
今後もこれまで培ってまいりました人とのつながりを最大限に生かしながら、上田市から飯山市までの流域7市町で構成されます、そして、私が会長を務めます千曲川改修期成同盟会などを通じて、またあらゆる機会を通じて、さらなる整備の前倒しを強く要望してまいりたいと思います。
次に、(仮称)治水対策研究会への取組についてお答えいたします。
令和元年東日本台風災害を契機に、令和2年度より行政と流域住民が一体となり、私が会長を務めます芹田長沼間をはじめ、篠ノ井、松代、若穂、更北の各地区における千曲川関係5団体が合同で国に対し、要望活動を実施しております。
今までは個々に実施しておりました同盟会の要望活動を、新たに合同で企画したことで、より強い要望となったものと考えております。令和4年度には千曲川関係の5団体に加え、市内を流れる河川ごとに設立されております期成同盟会の代表者が一堂に会し、治水対策や流域治水に関する研究や意見交換を行う機会を設け、その場で出された住民間の意見につきましては、確実に河川管理者に伝えてまいりたいと思います。
また、住民参加による流域治水につきましても、意識啓発に努め、あらゆる関係者が一体となり、治水安全度向上に向け取組を推進してまいります。
鈴木:先ほどの5団体のうちの4つが南部なんです。南部の団体で、これまでも期成同盟会、いろいろ御活動をされてきましたけれども、やはり状況がどんどん変わってきているということと、先ほども御紹介したように河川整備計画の変更等々、非常に流域住民にとっては重要な課題でありますので、まずは1から期成同盟会の中でもそれぞれの地域の課題しっかりと洗い出していくような取組としていっていただいて、大きな塊で要望活動していっていただくことを改めてお願いをしたいと思います。
③市指定文化財旧作新学校本館改修整備について
次に、長野市指定文化財旧作新学校本館改修整備について伺います。
去る1月20日、同館改修委員会が設立され、また、昨年10月、前市長宛てに更北住民自治協議会が作新学校本館改修について要望書を手交しました。要望書は資料展示室のほか、子供たちの育成の場、さらに地域と学校をつなぐ施設となることを求めています。
しかし、1月22日付の信濃毎日新聞の記事によりますと、要望どおりの改修について市が難色を示していることから、同委員会は地元の思いを形とすべく募金活動への取組を始めようとしている、とのことであります。
長野市は地元の願いを真摯に受け止め、確実な財源確保の道を探っていただきたいと思いますが、一例といたしまして、長野県は地域の元気を生み出すモデル事業に対し、地域発元気づくり支援金を交付しております。交付対象事業は、地域郷土の推進教育及び文化の振興等に則した取組などを条件としていますが、旧作新学校本館改修整備事業は、これらの趣旨に合致しているものと考えます。
支援金の交付を受けるためには、要領の第6項以後の定めに基づき、回収にかかる見積もり等が必要となることから市の積極的な関与が求められます。改修整備を進めるために、市は地元とともに地域発元気づくり支援金の認可に向け、取り組むことができないでしょうか。
また、市町村が交付対象者の場合の交付額が経費の2分の1以内であるのに対し、公共的団体等の場合は経費の3分の2以内となっていることから、改修委員会等と協議を行い、より有利な公共的団体等して適用されるよう取り組むことができないか。さらに、令和4年予算に耐震診断、耐震強度設計、実施設計等が計上されていますが、市として当館改修整備を優先事業と位置付け、進めていただくことを強く要望をさせていただき、新年度以降の具体的な改修計画をどのように策定されているのか、伺います。
教育次長:旧作新学校本館は、明治16年の建築で、明治10年代の洋風学校建築の姿をよく残している建物として、昭和56年に市の有形文化財に指定したものでございます。その後、必要な都度修理を実施し、本年度も雨漏りや床の腐朽に対する応急対策を行ったところですが、当初の建築から150年、移築から50年となるのを目前に、傷みが激しくなっております。
そのため、耐震対策を含め全面的な舗装修理に向けた準備として、平成30年度には劣化調査、令和元年度には 設計を行ってまいりましたが、令和元年東日本台風災害以降、進捗に遅れが生じており、下氷鉋小学校開校150周年に向けてリニューアルを希望する、地元の皆様の御期待に沿うことが難しくなっていったものでございます。
このような状況を受け、本年1月、地元更北地区で新たに改修委員会を組織して、旧作新学校本館の新たな活用構想の検討や資金集めの準備を始めていただいたことを、大変心強く思っております。
御質問のうち、地域発元気づくり支援金の認可に向けて地元と共に取り組めないか、ということでございますが、旧作新学校本館の整備事業は議員御指摘のとおり、県の地域発元気づくり支援金の要綱に定める要旨に合致しているものと考えております。長野地域振興局へ問い合わせるなどして、制度の活用に向けて現在情報収集をしているところでございます。
財源の確保に向けましては、このほかにも活用できる制度がないか検討してまいりますが、まずは、地元の皆様と共に、支援金の交付を目指してまいりたいと考えております。
また、元気づくり支援金の申請団体についての御提案でございますが、建物内部を活用するためのソフト事業については、地元改修委員会が主体の事業にすることで、より有利な補助率の公共的団体として申請することも可能ではないかと考えておりますので、今後、地元の皆様と協議してまいります。
なお、建物本体の保存修理については、市が発注する修理施設の工事ですので、市が申請団体になるものと考えております。
来年度以降の計画について、改修整備に要する全体事業費や工期等の詳細は、新年度に予定しております耐震診断及び実施設計により明らかになってまいりますので、現時点ではっきりとは申し上げられませんが、令和5年度以降、できるだけ早期の着手、完了を目指してまいります。
このたびの旧作新学校本館の整備事業は、活用構想の検討や資金面などで地元の皆様と共同しながら進めていくことになります。旧作新学校本館を子供たちの育成の場、さらには地域と学校をつなぐ場として整備し、末永く次世代に継承していくという地元の皆様の思いの早期実現に向けて、今後も引き続き関係する皆様と、協議調整を継続してまいりたいと考えております。
④川中島古戦場史跡公園整備について
鈴木:本当に地元の皆様方、本当に熱意を持って取組が現在進められているところでございます。建物は僕もよく知っていますが、実は僕も卒業生ですが、中に入った記憶がないというものでございますので、ぜひとも入ってみたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、川中島古戦場史跡公園整備について、伺います。
昨年度、市と地元で構成された川中島古戦場史跡公園活性化検討会議が行われ、その中での方向性に基づいて、令和3年度予算により、古戦場史跡公園整備がおおむね計画どおり進められたと理解しております。
しかし、地元の方々からはさらなる整備と基本的な公園の将来像や、コンセプトの議論が不十分なのではないか、観光客の車やバスがハンドルを切りたくなるような整備が必要ではないか、今風の食事処やカフェはどうか、そうしたセンスのある店舗が必要なのではないか、といったようなお声をこのところお聞きをさせていただいております。
そうした御要望にもしっかりとお答えするために、決して今回の整備で終わりというものではなくて、川中島古戦場史跡公園活性化を観光戦略の上位と位置付け、新年度以降も地元や多くの市民、特に若者の意見をお聞きし、その上で専門家を招聘するなど、さらなる検討を重ねて地域振興、観光振興につながる事業として、強化することを強く求めたいと思いますが、御所見を伺います。
都市整備部長:川中島古戦場史跡公園の再整備に関しましては、更北まちづくり委員会及び更北地区住民自治協議会から御提案をいただいた活性プランを参考に、公園、観光、博物館など庁内関係部局間で連携し、活性化にかかる事業を実施してまいりました。
事業の実施にあたっては、地域の活動として定着してきた古戦場まつりなどを発展させながら、賑わいの創出につながるよう、今年度は古戦場の雰囲気が感じられる広場や休息所のほか、イベント時の移動販売スペースなども整理し、秋には古戦場内等をめぐるデジタルスタンプラリーやデジタルマップなど、新たな誘客事業を実施してまいりました。
今後の観光戦略につきましては、次期観光振興計画において、古戦場を松代地区とともに観光振興の主要な拠点の1つとして捉えており、善行寺御開帳の期間中、バージョンアップしたデジタルスタンプラリーの実施や善光寺、古戦場、松代間でライナーバスを運行するなど、周遊に踏み込んだ誘客を促進してまいります。
また、長野インターに近い川中島古戦場は、立地上の集客ポテンシャルが高いことから、古戦場を印象付けるのぼり旗など、観光客を引きつける仕掛けにより、周辺幹線道路からの誘導に努めるとともに、博物館では川中島の戦いの展示を充実させ、集客拡大につなげてまいります。さらに、古戦場では地元が主催する三太刀まつりや古戦場まつりなど、イベントが定着し、軽トラ市も行われておりますが、今回の整備で生まれたスペースで、キッチンカーによる販売なども可能になったことから、活動がさらに充実し、活性化につながるものと期待しております。現在、公園内では、休息所の陣幕をバックに記念撮影をする観光客の姿が見られるなど、新たな流れが生まれております。
今後もこうした観光客の動向や地域の活動を踏まえつつ、知名度が高い川中島の戦いをテーマとして、地元の皆様の幅広い御意見や必要に応じた専門家の御意見もお聞きしながら、観光資源としての魅力の増進に努めてまいります。
鈴木:幅広い、かつ継続的に議論進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上となります。全文をお読みになられた皆様、ありがとうございました。一問一答でのやりとりですが、その場で答弁を100%理解するには至らないところもあり、 再度の質疑に繋がらない等、反省点が多々あります。
それでも、こうしたやりとり積み重ねることで、市民の皆様からいただいた貴重な一般質問の場を通し、持続可能な地域づくりへと確実に繋がるよう、邁進して参ります。
①新型コロナ関係
鈴木:長野市の感染の拡大防止に係る対策について、専門的知識及び意見を反映させることを目的として、新たに「長野市新型コロナウイルス感染症有識者会議」を設け、昨年12月22日以降3回の会議を開催しておりますが、改めて有識者会議の位置づけのほか、幾つかお伺いをいたします。
長野市における新型コロナウイルス感染状況は、1月8日以降急激な感染拡大期に入り、1月13日には県の感染警戒レベルが5に引上げられ、翌14日、長野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、長野市新型コロナウイルス感染症対応方針の改定と市長メッセージが発出されました。
しかし、こういうときにこそ有識者会議を開催し、市としての対応方針や市長メッセージに生かすべきではないでしょうか。市長が公約で掲げた(仮称)感染症対策調査チームは、保健所内に構成するとしていたことから、私なりに政府の基本的対処方針分科会や、厚労省アドバイザリーボードといったような感染症や医療の専門家から、基本的な感染拡大防止対策や、本市の現状を踏まえた具体的な提言を求めたかったのではないか、と受け止めました。国や県の対応方針を基本としつつ、感染状況の情報収集と解析により、長野市独自の対応方針を導き出すための有識者会議であるべきではないか、と考えます。
ぜひ、有識者会議を明確に位置づけ、形式的な会議に終わらせることがないよう強く求めたいと思います。
そこで、基本的なことをお聞きしますが、長野市は有識者会議をどう位置づけているのか。また、有識者会議との関係において、対応方針の改定手続は適切だったのか、伺います。
市長:まず、有識者会議の位置づけでありますが、本市の感染状況等を踏まえまして、私が本部長である「長野市新型コロナウイルス感染症対策本部」に対して、保健、医療、経済活動などの専門的知見からアドバイスをいただくという会議です。
特に、4月からの善光寺御開帳期間中に、様々なイベントが開催され、多くの参拝客や観光客などが長野市にお越しになりますので、関連する催事が安心安全に開催されるために、主催者が作成し、県に提出いたします感染防止安全計画等に対しても、御意見をいただいている、ということでございます。これまでに3回の会議を開催し、有益な御助言を頂戴してまいりました。
続きまして、市の対応方針の改定手続についてですが、国の基本的対処方針や県の対応方針の見直し、あるいは県において感染警戒レベル変更などが行われた際に、本市の取組の全体的な方針について、対策本部において改定を決定しているものでございまして、適時適切に改定しております。
有識者会議設置後は、市の対応方針に対して、有識者会議から御意見をいただき、必要があれば改定を行うこととしております。 以上です。
鈴木:私も、3回傍聴させていただいている中での印象ですが、やはりどことなく説明の場、そうした会議となっているのではなか、と受け止めております。この有識者会議の設置目的に、感染拡大防止策、先ほどの、例えば御開帳等の対応も当然必要だけれども、やはり肝腎の感染拡大防止についての議論はやや少ないのではないか、と感じておりますので、その辺は指摘をさせていただいて、次回、今月行われるかと思いますが、そちらのほうにしっかりと反映をしていただきたいと要望させていただきます。
本年1月の市内における感染急増の背景には、同居家族の感染者数の増大がありました。
1月下旬、家庭内感染により陽性者となった私の知人の事例では、保育園に通うお子さんのクラスで、園児数名が発熱により園を休み、その後、当該クラス全ての園児が濃厚接触者となり、検査の結果、知人のお子さん、続けて、私の知人夫婦も陽性となりました。
詳細は割愛しますが、知人夫婦が濃厚接触者との判定がなされるまでの数日間、通常通りの生活を送ることが可能であったとのことであります。陽性となったお子さん、小さなお子さんがいる家庭では、保護者等の家族はお子さんとの接触は避けられず、罹患するリスクは極めて高く、さらに無症状がゆえに、市中感染を拡大させる可能性をも高めます。
以上のことから、集団生活を送る施設等における感染拡大防止について伺います。
保育園のような集団生活を送る施設内において、1人でも発熱等の感染が疑われる症状が発生した場合、すぐにPCR検査を受けてもらうなど、感染拡大防止に迅速に取り組むことが求められます。
保健所は、保育園等の施設との間で、各施設が利用者の体調管理等、確認すべき事項について整理し共有できているのでしょうか。また、パンデミックの際、それぞれの施設内で窓口となる責任者を明確にし、保健所と情報や対応策等について、迅速に共有を図れるような仕組みを構築することが必要ではないでしょうか。
さらに保健所は、保育園や保護者に対し、保健所や医療機関での迅速な検査につなげるなどの支援体制を整えているのでしょうか。
保健所長:施設の利用者の体調管理などの、確認すべき事項の整理と共有についてですが、保健所では第1波の感染拡大を受けて、令和2年の7月と9月に、学校、保育所、高齢者障害者等の施設向けの研修会を延べ9回開催いたしまして、参加いただきました500名の方に対しまして、利用者及び従事者の健康確認、感染予防の基本、感染者が発生したときの具体的な対応等を説明し、施設内での徹底を依頼しました。
また、この研修会で使用したマニュアルは、県と合同で作成したものでありますが、市保健所のホームページにも掲載をいたしまして、各施設で利用できるよう、広く周知をしております。
次に、施設の窓口の明確化と迅速な情報共有の仕組みについてですが、施設で感染者が発生した場合には、私どもが直接、または所管部署を通じて、直ちに当該施設に連絡をいたしまして、感染者の発生状況や感染対策の状況などを把握するとともに、必要に応じまして現地に赴いて、さらに情報収集や具体的な対策の助言などを行っておりまして、迅速な情報共有を図っているところであります。
次に、保育園や保護者に対する迅速な検査につなげる等の支援体制についてですが、保健所では感染が判明した当日、または翌日には感染者と施設に対して詳しい聞き取りを行いまして、濃厚接触者を特定するとともに、検査の適切な時期であります、感染が考えられます3日から5日後に検査を実施し、また既に症状がある方については、速やかに医療機関を受診し、検査を受けるよう指導しております。
鈴木:先ほども御紹介したとおり、例えば発熱の症状があるような場合というのが、今回のオミクロン株の特性等を考えてみると非常に重要だと思います。例えば、施設の中で検査は陽性かどうか、オミクロンかどうか、コロナかどうかは分からないが、そういった症状があった場合に保健所といろいろなコミュニケーションがとれるような仕組み、そうした体制が、例えば、これからBA.2とかいろいろ言われていますが、必要じゃないか、と思いますが、いかがでしょうか。
保健所長:保育所等において、利用者または広く従事者も含めてですが、何らかの症状が見られた場合には、市内にあります診療検査医療機関を速やかに受診をしていただくことが肝要であります。保健所への連絡を通してからの受診ではなくて、まず症状があったら受診、このことはしっかり徹底をしていきたいと思っております。その上で、新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、医師から届出が来ますので、その
上でしっかり施設や、御本人方の情報収集を行って対応していくことになっています。
鈴木:今の部分、徹底よろしくお願いいたします。同居家族のうち1人でも濃厚接触者となった段階で、同居する全ての家族に対し、検査結果が判明するまでの間、ウイルスの特性に応じた対応策を講じる必要があるのではないでしょうか。
例えば、施設内で複数人の感染が疑われる場合、施設に通う人はもちろん、その同居家族に対し、行政として行動自粛等を強くお願いするべきではないでしょうか。
保健所長:濃厚接触者の同居している家族等への対策について、濃厚接触者がいらっしゃって、確かに感染の可能性はありますが、その方が発症もしていない、また、まだ検査で感染も判明していない段階において、その方が必ず感染しているとまでは言えませんので、行動自粛といった強い要請を行政から一方的に行うことはやはり適切ではないと考えております。
しかしながら、感染の可能性があることは事実でありますので、保健所では、濃厚接触者であることが判明した時点で、同居の方との生活空間をしっかり分け、マスクの着用と手指消毒、物品の消毒などの感染防止対策を徹底するように指導しておりまして、濃厚接触者が仮にお子さんのような場合でありますと、こういった対応が困難なことが予想されますので、そういった場合には、濃厚接触者の検査の結果が出るまでは、外出を控えていただくようお伝えをしてございます。引き続き、個々の状況を踏まえて、適切に対応し、感染拡大防止に努めてまいりたいと思っております。
鈴木:こちらのほうも、重ねてお願いをしたいと思います。昨年3月の定例会代表質問において、救急搬送先の決定困難事例について取上げましたが、報道によりますと、新型コロナウイルス感染が第6波に入った今年の1月下旬、長野市消防局管内で救急搬送困難事例が3件あり、特に1月25日の市内の90代女性の場合、医療機関に受入れを6回照会し、搬送開始までに1時間2分かかったとのことであります。
1月下旬の市内における救急搬送困難事案について、市消防局警防課は、現時点で都市部のように救急搬送体制が逼迫した状況ではない、また、医療機関の病床逼迫が原因かどうか判断できない、との見解を示されていました。
2月8日時点の、県全体の確保病床使用率は44.4%でしたが、北信ブロックにおける確保病床使用率は71.9%であったことから、1月下旬には病床逼迫の影響が出ていたのではないか、と推察しますが、医師の判断により、入院措置が必要とされた新型コロナウイルス感染者を確実に入院できていたのか、また、なぜ搬送開始まで1時間以上かかったのか、その原因は何だったのか、改善が図られたのか。
保健所:私から、入院が必要な感染者の入院の状況についてお答えいたします。本市の入院患者が最も多かった1月30日において、長野医療圏と北信医療圏を合わせたいわゆる北信ブロックでありますけれども、病床確保数128床に対して104人が入院しておりまして、病床使用率81.3%でありました。この数字から、病床に決して余裕があるとまでは言いませんけれども、入院が必要とされる感染者の入院病床は、これまでのところ確保されていると考えております。
消防局長:私からは、困難事案につきましてお答えをいたします。最初に、消防局管内における国の基準に基づく搬送困難事案の状況でございますが、本年1月1日から2月末日までの間に3件の事案がございまして、前年同期との比較では、1件のマイナスという状況でございます。
また、総務省消防庁が公表してございます全国52消防本部の中では、2月20日の時点で5番目に少ない状況となっております。
御質問の事案でございますが、119番通報により出動した救急隊は、一般の傷病者として、医療機関へ受入れの問合せを開始したところ、他の救急事案に対応中で、処置困難との理由から受入れに至らず、照会が3回に及んだこと、また、症状などを確認する中で、新型コロナウイルス感染症が疑われたことから、医療機関との照会に3回を要したこと、その結果、医療機関への照会回数が6回となり、搬送開始までに1時間を要したものでございました。
後日、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の救急搬送の件につきましては、保健所と医療機関において改めて確認をいただきまして、2月に入ってから、同様のケースの救急搬送におきましては、全てスムーズな受入れがなされてございます。
なお、本年2月末日までの救急出動3,339件のうち、約99%は救急隊からの照会が2回以内で搬送先が決定している状況でございまして、救急搬送業務におきましては、各医療機関には円滑な対応をいただいているものと考えてございます。以上でございます。
鈴木:ありがとうございました。 しっかりと対応を引き続きお願いしたいと思います。オミクロンの急増期であった冬季は、脳出血、心筋梗塞などの患者が多い時期でもあり、一般の救急が滞れば手後れとなる患者の続出が懸念されます。
オミクロン株は従来株に比べて重症化しにくいと言われていますが、感染爆発による医療逼迫をいかに回避するかが一番の課題であることから、宿泊療養と自宅療養を含めた医療全体のリソースを確保するために、自宅療養の在り方が重要だと考えます。
保健所が自宅療養者に対し、電話での健康観察を行い、仮に容体が悪化した場合、かかりつけ医、輪番医への診療を依頼されているとのことですが、迅速な対応が取れているのでしょうか。具体的な手順はどのような内容となっているのでしょうか。
また、かかりつけのクリニックや薬局を含めた地域の関係機関全体で、自宅療養者に医療行為を提供できる体制の構築が急務ではないかと考えますが。
保健所長:自宅療養者の容体が悪化した場合の対応についてですが、第6波で自宅療養者が700人を超える日もありましたけれども、保健所による毎日の健康観察や、感染者の方からの御相談において症状の悪化が認められる場合には、かかりつけ医など診療可能な医療機関に保健所から連絡をして、薬の処方等をしていただくとともに、症状の悪化が著しい場合や夜間等でかかりつけ医などの対応が難しい場合には、私どもが連絡を受けた上で、長野医療圏で定めております輪番の病院に診療や入院をお願いし、また救急搬送が必要な場合には、保健所から救急隊の要請を行うなど、自宅療養者への迅速な医療の提供に努めているところであります。
なお、こうした対応については、24時間対応をしているところでございます。
次に、自宅療養者へ医療行為を提供する体制についてですが、第6波の感染急拡大に対応するため、医師会の御協力をいただきまして、2月1日、市内の医療機関を対象に、症状が悪化した自宅療養者に対する診療や処方が可能かどうかなどを調査したところ、かかりつけ医の患者であれば可能とした医療機関51か所、初診の患者でも可能としたところが33か所、抗ウイルス薬の治療も可能41か所などとなっておりまして、改めて、こうした医療機関、また関連する薬局の活用を図ることによりまして、自宅療養者への医療の提供の確保を図っているところであります。
鈴木:長野県において、1月27日から3月6日までまん延防止等重点措置が適用され、市は国や県の方針に基づき、新型コロナウイルス感染症対応方針の改定や、市長メッセージの発出等の取組が行われてきましたが、顕著な効果があったと考えていいのでしょうか。
例えば、定点観測により、本市の人流抑制や、人数制限等の実態がどう推移したのか数値で把握するとともに、市の対応方針、市長メッセージの内容や発出方法などについて、有識者会議の意見等も聞きながら、幅広い観点から分析評価し、今後の取組に生かしていくべきではないでしょうか。
市長:令和2年5月以降、市の対応方針や市長メッセージは、感染警戒レベルが高くなった際などに発信し、動画をホームページへ掲載しております。その効果についての御質問ですが、国、県の取組を踏まえて、本市としての全体的な取組の方向性を示すことや、私が直接市民の皆様へ呼びかけることにより、市の対策や姿勢を発信するという役割を果たしているというふうに考えてございます。
また、発信した情報により、市民の皆さん、事業者の皆様が感染予防を徹底していただく一つのきっかけになったと思っています。なお、その効果が顕著であったかにつきましては、判断基準については持ち合わせておりません。
次に、人流抑制や人数制限の推移についてですが、これらは基本的に特措法に基づく県知事の要請でありまして、市としては推移の把握は行っておりません。市対応方針の内容や市長メッセージ等については、市の対策を取りまとめて、市民の皆さん、事業者の皆様に御協力をお願いするための情報発信であり、感染状況に応じて見直していることから、今後も有識者会議からの御意見も生かしながら、適時適切に改定してまいります。
新型コロナウイルス感染症対策については、国、県、市の役割分担の中で、皆様の御理解と御協力をいただきながら、本市として最大限の取組を実行してまいります。
②信濃川水系河川整備と治水対策について
鈴木:いろいろ御腐心続いておられるかと思います。これまでの取組には敬意と感謝を申し上げさせていただきつつ、これからもよろしくお願いをしたいと思います。
次に、信濃川水系河川整備計画変更骨子案と治水対策について伺います。
信濃川水系河川整備計画変更骨子案が策定され、改訂に向けた検討が進められています。そもそも千曲川犀川を含む信濃川水系の河川整備は、平成20年6月に策定された信濃川水系河川整備基本方針で、立ヶ花及び杭瀬下地点における計画高水流量を毎秒9,000立方メートル、5,500立方メートルと定め、それとは別におおむね30年かけて具体的な工事を行うため、平成26年1月に策定された信濃川水系河川整備計画では2か所の河道配分流量を、基本方針の計画高水流量を大きく下回る毎秒7,300立方メートル、4,000立方メートルとしていました。
そして整備途上にあった令和元年に台風第19号災害が発生し、そのときの流量は2か所とも整備計画の河道配分流量を大幅に上回り、さらには基本方針が定めた計画高水流量を杭瀬下では大幅に上回り、立ヶ花についても設定値に迫る勢いだったのであります。
台風第19号の洪水を受け、現在、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトに基づく整備が進められていますが、整備計画を改訂し、プロジェクトとの整合性を図ることが必要であると理解しています。
そこで骨子案を見ますと、基準地点である立ヶ花の河道配分流量、毎秒8,300立方メートルへの改定は、台風第19号時の流量である毎秒8、387立方メートルの近似値ですが、長野市の上流に位置する杭瀬下地点における河道配分流量を、毎秒4,900立方メートルとしていることには理解が及びません。
台風第19号時における杭瀬下地点の流量は、残念ながら国は定められている観測ができなかったとしていますが、杭瀬下上流の観測地点である生田での流量を毎秒7,267立方メートルとしていることから、理論的には杭瀬下地点での流量はそれ以上とみられます。
仮に、生田の7,267立方メートルがそのまま流下したとしても、信濃川水系河川整備計画変更骨子案で提示している杭瀬下地点の河道配分流量、毎秒4,900立方メートルを2,367立方メートル上回る流量となり、杭瀬下の下流域である篠ノ井から若穂に至る流域住民には到底、受け入れがたいものであります。
これまでの整備計画は限られた諸条件の基で、整備の実現性を優先に策定されたものだと推察しますが、今回は台風第19号での大災害を受けたのであり、将来にわたり住民の生命と財産を守り切る立場から、現実に起こった値、つまり実績値を基本に河川整備計画の河道配分流量を検討すべきであります。
長野市は骨子案にある杭瀬下地点の河道配分流量をいかに受け止めているのか、また台風第19号時の杭瀬下地点での実績値を基本とした河道配分流量へと見直しを強く求めるべきではないか。さらに上流の杭瀬下が定まれば、立ヶ花の毎秒8,300立方メートルを再考する必要があると考えますが。
建設部長:信濃川水系緊急治水対策プロジェクトでは、令和元年東日本台風災害の洪水実績に対し、令和9年度までの、令和元年洪水における千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水被害を防止することとしております。
現在、手続を進めている信濃川水系河川整備計画の目標原案においては、さらなる治水安全度向上のため、基準地点である立ヶ花においては、戦後最大を更新した令和元年10月洪水と同規模の毎秒9,400立方メートルを目標流量とし、河道配分流量を毎秒8,300立方メートルとして堤防の決壊、越水等による家屋の浸水被害の防止または軽減を図ることとしております。
議員御質問の内容について、国土交通省、北陸地方整備局、千曲川河川事務所に問い合わせたところ、杭瀬下地点の河道配分流量を毎秒4,000立方メートルから4,900立方メートルに引き上げたことについては、令和元年10月洪水規模に対し、信濃川水系河川整備基本方針で最終目標である計画高水流量5,500立方メートルに向け、基準地点立ヶ花をはじめ、下流域を含めた上下流バランスを考慮した上で設定された流量であるとのことでありました。
変更原案で示されている内容のうち、上流のダムや新設される遊水地などの洪水調節施設による調節流量が立ヶ花地点においては毎秒1,100立方メートルとされております。そのうち、流域治水という観点から、流域自治体が一定量の調節量を担うことから、事を国から求められていることもあり、市では具体的な取組を推進するため、国の考えを確認している状況です。
現在、国では河川整備計画変更原案に対する住民意見募集を開始しており、その後に市を含めた関係機関協議が行われる予定です。市では自治体における流域治水上の調節量に加え、議員御質問の河道配分流量の見直しの点についても、その数値の妥当性について確認してまいりたいと考えております。
鈴木:今、御答弁あったとおり、この妥当性、非常に大事だと思っております。例えば、先ほど1,100立方メートルですか、この具体的な数値をあてがっていかないと、4,900、これは大丈夫なんですかと。基本方針だって5,500ですよ。5,500に対して7,000トンを超える流量が流れてきたという事実をしっかりと受け止めて、長野市のほうとしても、また調査していただいて、必要な要望はしていっていただきたいということを求めたいと思います。
市長は昨年の選挙公約で、これまで培ってきた人とのつながりを生かし、国や県への働きかけを強め、東日本台風災害へのさらなる支援を強力に要望していくと掲げられました。そのためにはまず台風第19号の際、杭瀬下の下流域の篠ノ井から若穂に至る間において、越流、浸水と甚大な被害が発生したことを踏まえ、長野市南部の安全性についてもっとも重要な数値である立ヶ花と杭瀬下地点の河道配分流量の実績値を基本に改訂するよう強く働きかけ、台風災害で甚大な被害を受けた自治体のリーダーとして、災害に強いまちづくりに向け、全力で取り組んでいただくことを期待しますがいかがでしょうか。
また、市長は施政方針の中で、緊急対策の1つとして防災復興を取り上げ、(仮称)治水対策研究会を設置と防災・減災を強化するとしています。昨年12月定例会で布目議員への答弁で、千曲川関係5団体での合同要望活動をバージョンアップさせる形で取り組むとしていますが、やや不十分かなと受け止めております。大事なことは今までの延長線ではなく、流域住民のリスクや不安などの切実な声、要望等を受け止め、市と一体となった取組としなければならないと考えますが。
市長:信濃川水系河川整備計画の変更の手続につきましては、国において河川法に基づき、進められているものと考えております。先に示されました変更原案では、河川整備基本方針で定めた目標に向けて、過去の洪水における洪水特性や現在の河川整備状況、上下流、本支川の整備バランスとを総合的に勘案し、段階的かつ着実な河川整備を実施することで、戦後最大規模の洪水に対し、災害発生の防止または軽減を図る
とされております。杭瀬下地点の河道配分流量についても、その考えに基づき適切に設定されていると理解しております。
令和4年中に予定されております関係機関との協議などを通じて、その数値について改めて確認するとともに、仮に疑義が生じているような部分があれば、私がしっかり意見を申し立ててまいりたいと思っています。
また、今回の計画変更により、河川整備計画に位置付けられる信濃川水系緊急治水対策プロジェクトにおける流水域整備、河道掘削等の河川における対策が確実に実施されることで、長野市南部を含めました市全域における治水安全度が向上することから、本年1月にはオンラインにより、国土交通大臣政務官に整備計画の前倒しの要望を行いました。
今後もこれまで培ってまいりました人とのつながりを最大限に生かしながら、上田市から飯山市までの流域7市町で構成されます、そして、私が会長を務めます千曲川改修期成同盟会などを通じて、またあらゆる機会を通じて、さらなる整備の前倒しを強く要望してまいりたいと思います。
次に、(仮称)治水対策研究会への取組についてお答えいたします。
令和元年東日本台風災害を契機に、令和2年度より行政と流域住民が一体となり、私が会長を務めます芹田長沼間をはじめ、篠ノ井、松代、若穂、更北の各地区における千曲川関係5団体が合同で国に対し、要望活動を実施しております。
今までは個々に実施しておりました同盟会の要望活動を、新たに合同で企画したことで、より強い要望となったものと考えております。令和4年度には千曲川関係の5団体に加え、市内を流れる河川ごとに設立されております期成同盟会の代表者が一堂に会し、治水対策や流域治水に関する研究や意見交換を行う機会を設け、その場で出された住民間の意見につきましては、確実に河川管理者に伝えてまいりたいと思います。
また、住民参加による流域治水につきましても、意識啓発に努め、あらゆる関係者が一体となり、治水安全度向上に向け取組を推進してまいります。
鈴木:先ほどの5団体のうちの4つが南部なんです。南部の団体で、これまでも期成同盟会、いろいろ御活動をされてきましたけれども、やはり状況がどんどん変わってきているということと、先ほども御紹介したように河川整備計画の変更等々、非常に流域住民にとっては重要な課題でありますので、まずは1から期成同盟会の中でもそれぞれの地域の課題しっかりと洗い出していくような取組としていっていただいて、大きな塊で要望活動していっていただくことを改めてお願いをしたいと思います。
③市指定文化財旧作新学校本館改修整備について
次に、長野市指定文化財旧作新学校本館改修整備について伺います。
去る1月20日、同館改修委員会が設立され、また、昨年10月、前市長宛てに更北住民自治協議会が作新学校本館改修について要望書を手交しました。要望書は資料展示室のほか、子供たちの育成の場、さらに地域と学校をつなぐ施設となることを求めています。
しかし、1月22日付の信濃毎日新聞の記事によりますと、要望どおりの改修について市が難色を示していることから、同委員会は地元の思いを形とすべく募金活動への取組を始めようとしている、とのことであります。
長野市は地元の願いを真摯に受け止め、確実な財源確保の道を探っていただきたいと思いますが、一例といたしまして、長野県は地域の元気を生み出すモデル事業に対し、地域発元気づくり支援金を交付しております。交付対象事業は、地域郷土の推進教育及び文化の振興等に則した取組などを条件としていますが、旧作新学校本館改修整備事業は、これらの趣旨に合致しているものと考えます。
支援金の交付を受けるためには、要領の第6項以後の定めに基づき、回収にかかる見積もり等が必要となることから市の積極的な関与が求められます。改修整備を進めるために、市は地元とともに地域発元気づくり支援金の認可に向け、取り組むことができないでしょうか。
また、市町村が交付対象者の場合の交付額が経費の2分の1以内であるのに対し、公共的団体等の場合は経費の3分の2以内となっていることから、改修委員会等と協議を行い、より有利な公共的団体等して適用されるよう取り組むことができないか。さらに、令和4年予算に耐震診断、耐震強度設計、実施設計等が計上されていますが、市として当館改修整備を優先事業と位置付け、進めていただくことを強く要望をさせていただき、新年度以降の具体的な改修計画をどのように策定されているのか、伺います。
教育次長:旧作新学校本館は、明治16年の建築で、明治10年代の洋風学校建築の姿をよく残している建物として、昭和56年に市の有形文化財に指定したものでございます。その後、必要な都度修理を実施し、本年度も雨漏りや床の腐朽に対する応急対策を行ったところですが、当初の建築から150年、移築から50年となるのを目前に、傷みが激しくなっております。
そのため、耐震対策を含め全面的な舗装修理に向けた準備として、平成30年度には劣化調査、令和元年度には 設計を行ってまいりましたが、令和元年東日本台風災害以降、進捗に遅れが生じており、下氷鉋小学校開校150周年に向けてリニューアルを希望する、地元の皆様の御期待に沿うことが難しくなっていったものでございます。
このような状況を受け、本年1月、地元更北地区で新たに改修委員会を組織して、旧作新学校本館の新たな活用構想の検討や資金集めの準備を始めていただいたことを、大変心強く思っております。
御質問のうち、地域発元気づくり支援金の認可に向けて地元と共に取り組めないか、ということでございますが、旧作新学校本館の整備事業は議員御指摘のとおり、県の地域発元気づくり支援金の要綱に定める要旨に合致しているものと考えております。長野地域振興局へ問い合わせるなどして、制度の活用に向けて現在情報収集をしているところでございます。
財源の確保に向けましては、このほかにも活用できる制度がないか検討してまいりますが、まずは、地元の皆様と共に、支援金の交付を目指してまいりたいと考えております。
また、元気づくり支援金の申請団体についての御提案でございますが、建物内部を活用するためのソフト事業については、地元改修委員会が主体の事業にすることで、より有利な補助率の公共的団体として申請することも可能ではないかと考えておりますので、今後、地元の皆様と協議してまいります。
なお、建物本体の保存修理については、市が発注する修理施設の工事ですので、市が申請団体になるものと考えております。
来年度以降の計画について、改修整備に要する全体事業費や工期等の詳細は、新年度に予定しております耐震診断及び実施設計により明らかになってまいりますので、現時点ではっきりとは申し上げられませんが、令和5年度以降、できるだけ早期の着手、完了を目指してまいります。
このたびの旧作新学校本館の整備事業は、活用構想の検討や資金面などで地元の皆様と共同しながら進めていくことになります。旧作新学校本館を子供たちの育成の場、さらには地域と学校をつなぐ場として整備し、末永く次世代に継承していくという地元の皆様の思いの早期実現に向けて、今後も引き続き関係する皆様と、協議調整を継続してまいりたいと考えております。
④川中島古戦場史跡公園整備について
鈴木:本当に地元の皆様方、本当に熱意を持って取組が現在進められているところでございます。建物は僕もよく知っていますが、実は僕も卒業生ですが、中に入った記憶がないというものでございますので、ぜひとも入ってみたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、川中島古戦場史跡公園整備について、伺います。
昨年度、市と地元で構成された川中島古戦場史跡公園活性化検討会議が行われ、その中での方向性に基づいて、令和3年度予算により、古戦場史跡公園整備がおおむね計画どおり進められたと理解しております。
しかし、地元の方々からはさらなる整備と基本的な公園の将来像や、コンセプトの議論が不十分なのではないか、観光客の車やバスがハンドルを切りたくなるような整備が必要ではないか、今風の食事処やカフェはどうか、そうしたセンスのある店舗が必要なのではないか、といったようなお声をこのところお聞きをさせていただいております。
そうした御要望にもしっかりとお答えするために、決して今回の整備で終わりというものではなくて、川中島古戦場史跡公園活性化を観光戦略の上位と位置付け、新年度以降も地元や多くの市民、特に若者の意見をお聞きし、その上で専門家を招聘するなど、さらなる検討を重ねて地域振興、観光振興につながる事業として、強化することを強く求めたいと思いますが、御所見を伺います。
都市整備部長:川中島古戦場史跡公園の再整備に関しましては、更北まちづくり委員会及び更北地区住民自治協議会から御提案をいただいた活性プランを参考に、公園、観光、博物館など庁内関係部局間で連携し、活性化にかかる事業を実施してまいりました。
事業の実施にあたっては、地域の活動として定着してきた古戦場まつりなどを発展させながら、賑わいの創出につながるよう、今年度は古戦場の雰囲気が感じられる広場や休息所のほか、イベント時の移動販売スペースなども整理し、秋には古戦場内等をめぐるデジタルスタンプラリーやデジタルマップなど、新たな誘客事業を実施してまいりました。
今後の観光戦略につきましては、次期観光振興計画において、古戦場を松代地区とともに観光振興の主要な拠点の1つとして捉えており、善行寺御開帳の期間中、バージョンアップしたデジタルスタンプラリーの実施や善光寺、古戦場、松代間でライナーバスを運行するなど、周遊に踏み込んだ誘客を促進してまいります。
また、長野インターに近い川中島古戦場は、立地上の集客ポテンシャルが高いことから、古戦場を印象付けるのぼり旗など、観光客を引きつける仕掛けにより、周辺幹線道路からの誘導に努めるとともに、博物館では川中島の戦いの展示を充実させ、集客拡大につなげてまいります。さらに、古戦場では地元が主催する三太刀まつりや古戦場まつりなど、イベントが定着し、軽トラ市も行われておりますが、今回の整備で生まれたスペースで、キッチンカーによる販売なども可能になったことから、活動がさらに充実し、活性化につながるものと期待しております。現在、公園内では、休息所の陣幕をバックに記念撮影をする観光客の姿が見られるなど、新たな流れが生まれております。
今後もこうした観光客の動向や地域の活動を踏まえつつ、知名度が高い川中島の戦いをテーマとして、地元の皆様の幅広い御意見や必要に応じた専門家の御意見もお聞きしながら、観光資源としての魅力の増進に努めてまいります。
鈴木:幅広い、かつ継続的に議論進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
以上となります。全文をお読みになられた皆様、ありがとうございました。一問一答でのやりとりですが、その場で答弁を100%理解するには至らないところもあり、 再度の質疑に繋がらない等、反省点が多々あります。
それでも、こうしたやりとり積み重ねることで、市民の皆様からいただいた貴重な一般質問の場を通し、持続可能な地域づくりへと確実に繋がるよう、邁進して参ります。