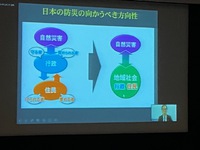九州熊本、球磨川の氾濫
2020年07月05日
鈴木洋一 at 12:06 | 活動
九州屈指の1級河川である球磨川氾濫の報道が飛び込んできました。球磨川は、その源を熊本県球磨郡銚子笠に発し、人吉・球磨盆地を貫流し、山間の狭窄部を流下し、八代平野に出て八代海に注ぐ、流路延長115km、流域面積1,880km2の河川です。
速報(時事通信)によると、7人死亡、14人心肺停止、重体1人、行方不明者が4人との報道であり、心よりご冥福とお見舞いを申し上げます。
7月5日付け信濃毎日新聞は、球磨川は上流から下流にわたり氾濫し、広範囲で冠水。人吉市内では約20m区間で堤防が決壊した、また、狭い川幅と水があふれやすい地形であった、と報じています。
国土交通省河川局は、平成19年5月に「球磨川水系河川整備基本方針」を策定していますが、私がインターネットで河川整備を進めていく上で策定する「河川整備計画」を探したところ、見つけることができませんでした。(探し方が甘かった可能性もあり、策定され公表されているかもしれません。河川法第16条の2は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画を定めておかなければならない、としていることから策定されているはず、ただ、熊本県河川課HP上から策定された記録が示されていない)
取り急ぎ、球磨川水系河川整備基本方針(以下、基本方針)を確認してみました。
<河川の概要>
上流部は、人吉・球磨盆地の田園地帯を蛇行しながら流下し、人吉市街部を貫流する。
中流部は、山間狭窄部で急流となっており、川岸は巨岩や奇岩が連なり瀬と淵が連続して交互に出現している。
下流部は、八代市街部を貫流する。
以上を見ると、報道であるように、上流から中流部に所在する山間狭窄部が治水対策上の課題だった、と解します。
<これまでの治水事業>
本格的な治水事業は、昭和12年に下流の八代地区(荻原地点)の計画高水流量を毎秒5,000tと定め、更に、昭和22年、上流の人吉地区(人吉地点)の計画高水流量、毎秒4,000tとし河道拡幅、築堤、掘削などの改修が行われたのが最初であった。
その後、昭和29年8月及び9月の出水を契機とし、昭和31年に計画を見直し、(今般、緊急放流について報道にあった)市房ダムで毎秒500tの調節を行うことで、基本高水流量を荻原地点、毎秒5,000tに人吉地点で毎秒4,000tとした。(市原ダムは昭和35年完成)
更に、昭和40年7月、当時の計画高水流量を上回る洪水に見舞われたことから、計画高水流量を荻原地点で毎秒7、000t、人吉地点では昭和22年と同じ毎秒4、000tとする工事実施基本計画を昭和41年4月に策定した。
この計画に基づき、上流の人吉では中心市街地の対岸において引堤※を実施。中流から一気に流下し、大きく湾曲した八代市街部で大規模な引堤、築堤、掘削、護岸整備等が実施された。(※川の流下能力を大きくするため、川の幅を拡大し既設の堤防を堤内地側に移動させること)
しかし、昭和57年7月、人吉地点で計画高水流量を大きく上回る洪水が発生、家屋損壊47戸、床上浸水1、133戸に及ぶ甚大な被害が生じ、更に、平成5年、7年、16年、17年の洪水時、人吉地点では計画高水流量と同程度の流量が発生し、中流部を中心に浸水被害が発生した。
ここまで、平成19年策定の基本方針から氾濫と治水工事についての概略です。その上で、私が確認したいことは、洪水調節機能を設けた上で計画高水流量が定められた、と受け止めますが、人吉地点での計画高水流量は、昭和22年は毎秒4、000t、昭和31年に毎秒4、000t、昭和40が年毎秒4、000tと、計画高水流量の改定がなされていないことです。
基本方針で定めた洪水調節機能の整備がどこまで行われていたのか、どこまで実効性が高まっていたのか、重要な確認事項だと思います。
<基本方針で定めた災害発生防止又は軽減について>
平成19年5月策定の基本方針は、河道や沿川の状況等を踏まえ、地域の特性にあった治水対策を講じ、具体的には堤防の新設、拡堤、河道掘削、護岸整備を実施する、としております。また、計画規模を上回る洪水及び整備途上段階での施設能力以上の洪水が発生し氾濫した場合においても、被害をできるだけ軽減させるために河道や沿川の状態、氾濫形態等を踏まえ必要な対策を実施する、とあります。
先にも記したように、球磨川の整備の基本となるべき事項において、洪水調節施設により流量を調節することで河道への配分流量を少なくする、とされていることから、過去の水害を考慮しながら計画高水流量の見直しや適宜対策工事を行ってきたとすれば、基本方針また整備計画に基づく基準そのものの妥当性(例えば、人吉地点の計画高水流量が据え置かれてきた点、計画高水流量の改定がなければ、計画高水位の見直しも無い可能性が高い)が疑われても仕方がない、と感じます。
そもそも、人吉地点では、何もしなければピーク時に毎秒7、000tの流量があり、基本方針で定めた毎秒4、000tを安全に流下させるために洪水調節施設で毎秒3、000tの調節が必要です。素人の机上の計算ですが、毎秒3,000tなので、仮に、1時間分を貯留させようとすれば180万トン規模の調節が必要となるのではないでしょうか。
今から10年以上前に策定された方針に基づき、どこまで実現されたのか、ここまでどんな進捗管理、検証、議論がなされてきたのか、その内容によっては行政や政治の責は大きいと感じます。
<各水害を教訓とし、流域市町村の役割が求められる時代>
私は、これまで市議会において1級河川である千曲川及び犀川に関する河川整備について、再三取り上げてきました。1級河川は国管理河川であることから、整備や管理の面で長野市は、直接的な事業展開は原則できません。(河川法第9条により都道府県知事、指定都市の長が行うことができる管理もある)
しかしながら、特に昨年に台風第19号により大きな被害を受けた長野市はもちろんのこと、1級河川を擁する地方自治体は、国だとか県だとか言っていられないはずです。流域住民である長野市民の生命と財産を守るために、積極的かつ主体的に関与し、市民の安全と安心につなげるための働きをしなければならないと考えます。
そうしたことから、私は引き続き、国管理河川でありますが、議会で取り上げ続けていくことが私の役割だと考えます。
球磨川の氾濫に関して、これから様々な専門家による検証がなされると思います。私もそれらの報告について自分なりに検証し、国の果たしてきた役割、県及び流域市町村におけるこれまでの取り組み、更に昨今の気候変動等を踏まえ、今、必要な河川整備とは何のか、捉えていけるように努力します。
速報(時事通信)によると、7人死亡、14人心肺停止、重体1人、行方不明者が4人との報道であり、心よりご冥福とお見舞いを申し上げます。
7月5日付け信濃毎日新聞は、球磨川は上流から下流にわたり氾濫し、広範囲で冠水。人吉市内では約20m区間で堤防が決壊した、また、狭い川幅と水があふれやすい地形であった、と報じています。
国土交通省河川局は、平成19年5月に「球磨川水系河川整備基本方針」を策定していますが、私がインターネットで河川整備を進めていく上で策定する「河川整備計画」を探したところ、見つけることができませんでした。(探し方が甘かった可能性もあり、策定され公表されているかもしれません。河川法第16条の2は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画を定めておかなければならない、としていることから策定されているはず、ただ、熊本県河川課HP上から策定された記録が示されていない)
取り急ぎ、球磨川水系河川整備基本方針(以下、基本方針)を確認してみました。
<河川の概要>
上流部は、人吉・球磨盆地の田園地帯を蛇行しながら流下し、人吉市街部を貫流する。
中流部は、山間狭窄部で急流となっており、川岸は巨岩や奇岩が連なり瀬と淵が連続して交互に出現している。
下流部は、八代市街部を貫流する。
以上を見ると、報道であるように、上流から中流部に所在する山間狭窄部が治水対策上の課題だった、と解します。
<これまでの治水事業>
本格的な治水事業は、昭和12年に下流の八代地区(荻原地点)の計画高水流量を毎秒5,000tと定め、更に、昭和22年、上流の人吉地区(人吉地点)の計画高水流量、毎秒4,000tとし河道拡幅、築堤、掘削などの改修が行われたのが最初であった。
その後、昭和29年8月及び9月の出水を契機とし、昭和31年に計画を見直し、(今般、緊急放流について報道にあった)市房ダムで毎秒500tの調節を行うことで、基本高水流量を荻原地点、毎秒5,000tに人吉地点で毎秒4,000tとした。(市原ダムは昭和35年完成)
更に、昭和40年7月、当時の計画高水流量を上回る洪水に見舞われたことから、計画高水流量を荻原地点で毎秒7、000t、人吉地点では昭和22年と同じ毎秒4、000tとする工事実施基本計画を昭和41年4月に策定した。
この計画に基づき、上流の人吉では中心市街地の対岸において引堤※を実施。中流から一気に流下し、大きく湾曲した八代市街部で大規模な引堤、築堤、掘削、護岸整備等が実施された。(※川の流下能力を大きくするため、川の幅を拡大し既設の堤防を堤内地側に移動させること)
しかし、昭和57年7月、人吉地点で計画高水流量を大きく上回る洪水が発生、家屋損壊47戸、床上浸水1、133戸に及ぶ甚大な被害が生じ、更に、平成5年、7年、16年、17年の洪水時、人吉地点では計画高水流量と同程度の流量が発生し、中流部を中心に浸水被害が発生した。
ここまで、平成19年策定の基本方針から氾濫と治水工事についての概略です。その上で、私が確認したいことは、洪水調節機能を設けた上で計画高水流量が定められた、と受け止めますが、人吉地点での計画高水流量は、昭和22年は毎秒4、000t、昭和31年に毎秒4、000t、昭和40が年毎秒4、000tと、計画高水流量の改定がなされていないことです。
基本方針で定めた洪水調節機能の整備がどこまで行われていたのか、どこまで実効性が高まっていたのか、重要な確認事項だと思います。
<基本方針で定めた災害発生防止又は軽減について>
平成19年5月策定の基本方針は、河道や沿川の状況等を踏まえ、地域の特性にあった治水対策を講じ、具体的には堤防の新設、拡堤、河道掘削、護岸整備を実施する、としております。また、計画規模を上回る洪水及び整備途上段階での施設能力以上の洪水が発生し氾濫した場合においても、被害をできるだけ軽減させるために河道や沿川の状態、氾濫形態等を踏まえ必要な対策を実施する、とあります。
先にも記したように、球磨川の整備の基本となるべき事項において、洪水調節施設により流量を調節することで河道への配分流量を少なくする、とされていることから、過去の水害を考慮しながら計画高水流量の見直しや適宜対策工事を行ってきたとすれば、基本方針また整備計画に基づく基準そのものの妥当性(例えば、人吉地点の計画高水流量が据え置かれてきた点、計画高水流量の改定がなければ、計画高水位の見直しも無い可能性が高い)が疑われても仕方がない、と感じます。
そもそも、人吉地点では、何もしなければピーク時に毎秒7、000tの流量があり、基本方針で定めた毎秒4、000tを安全に流下させるために洪水調節施設で毎秒3、000tの調節が必要です。素人の机上の計算ですが、毎秒3,000tなので、仮に、1時間分を貯留させようとすれば180万トン規模の調節が必要となるのではないでしょうか。
今から10年以上前に策定された方針に基づき、どこまで実現されたのか、ここまでどんな進捗管理、検証、議論がなされてきたのか、その内容によっては行政や政治の責は大きいと感じます。
<各水害を教訓とし、流域市町村の役割が求められる時代>
私は、これまで市議会において1級河川である千曲川及び犀川に関する河川整備について、再三取り上げてきました。1級河川は国管理河川であることから、整備や管理の面で長野市は、直接的な事業展開は原則できません。(河川法第9条により都道府県知事、指定都市の長が行うことができる管理もある)
しかしながら、特に昨年に台風第19号により大きな被害を受けた長野市はもちろんのこと、1級河川を擁する地方自治体は、国だとか県だとか言っていられないはずです。流域住民である長野市民の生命と財産を守るために、積極的かつ主体的に関与し、市民の安全と安心につなげるための働きをしなければならないと考えます。
そうしたことから、私は引き続き、国管理河川でありますが、議会で取り上げ続けていくことが私の役割だと考えます。
球磨川の氾濫に関して、これから様々な専門家による検証がなされると思います。私もそれらの報告について自分なりに検証し、国の果たしてきた役割、県及び流域市町村におけるこれまでの取り組み、更に昨今の気候変動等を踏まえ、今、必要な河川整備とは何のか、捉えていけるように努力します。