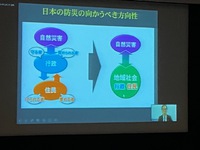ライフラインを守る
2018年11月16日
鈴木洋一 at 08:56 | 活動
先日13日、長野市若槻で水道管破裂事故が発生し、周辺の約4800戸に影響が及んでしまいました。
同地区の水道管は旧式のもので、1965年(昭和40年)に設置され一般的に標準耐用年数が40年と言われている中で、同地区の水道管は既に50年以上経過していることになります。
今回の事故は、13日のAM2:42頃に発生しましたが、その後、長野市上下水道局より、給水車を出動させ、また、懸命の復旧作業により同日の夕方には破裂箇所の修繕作業が完了、との報告を頂きました。
老朽管の更新については、度々、議会においても説明がなされているところではありましたが、今回の件を通し、長野市のみならず全県、いや、全国的にも将来に向け、老朽管の更新等の対策は大きな課題であるということを思い知らされました、市民の多くの方々も感じられたのではないかと思います。
2017年度末の長野市上水道管路総延長は2454kmで、このうち、埋設から40年を経過している老朽管が全体の17%にあたる414km存在しています。ということは、市内の17%の水道管が今回と同様の事故が発生する恐れがある、ということです。
そもそも水道事業は、地方公営企業として、水道料金などの収入により運営されており、その収入を基として、水道施設の運転、水道管の維持管理、職員の給与、借入金の利息の支払い等に使われています。
浄水場や管路の整備には多額の資金が必要となり、こうした資金は、企業債(つまり借金、公営企業なので企業債)、長野市の一般会計からの繰入などによって調達されております。
長野市水道局では、今後、概ね20km/年のペースで老朽管の更新を計画しており、まだまだ時間が掛かります。本当であれば、全ての管更新を早急に進めるべし!と強く望みたいところではありますが、急激な水道料金の値上げにも繋がりかねない一方で、上述のように、今回のような事案が市内のあちらこちらで起こらないとも言えません。
長野市における様々な事業があるわけですが、ライフラインをしっかり守るという観点から、行政、議会は優先順位をしっかり見極めなければならない時代であると再認識しなければなりません。
同地区の水道管は旧式のもので、1965年(昭和40年)に設置され一般的に標準耐用年数が40年と言われている中で、同地区の水道管は既に50年以上経過していることになります。
今回の事故は、13日のAM2:42頃に発生しましたが、その後、長野市上下水道局より、給水車を出動させ、また、懸命の復旧作業により同日の夕方には破裂箇所の修繕作業が完了、との報告を頂きました。
老朽管の更新については、度々、議会においても説明がなされているところではありましたが、今回の件を通し、長野市のみならず全県、いや、全国的にも将来に向け、老朽管の更新等の対策は大きな課題であるということを思い知らされました、市民の多くの方々も感じられたのではないかと思います。
2017年度末の長野市上水道管路総延長は2454kmで、このうち、埋設から40年を経過している老朽管が全体の17%にあたる414km存在しています。ということは、市内の17%の水道管が今回と同様の事故が発生する恐れがある、ということです。
そもそも水道事業は、地方公営企業として、水道料金などの収入により運営されており、その収入を基として、水道施設の運転、水道管の維持管理、職員の給与、借入金の利息の支払い等に使われています。
浄水場や管路の整備には多額の資金が必要となり、こうした資金は、企業債(つまり借金、公営企業なので企業債)、長野市の一般会計からの繰入などによって調達されております。
長野市水道局では、今後、概ね20km/年のペースで老朽管の更新を計画しており、まだまだ時間が掛かります。本当であれば、全ての管更新を早急に進めるべし!と強く望みたいところではありますが、急激な水道料金の値上げにも繋がりかねない一方で、上述のように、今回のような事案が市内のあちらこちらで起こらないとも言えません。
長野市における様々な事業があるわけですが、ライフラインをしっかり守るという観点から、行政、議会は優先順位をしっかり見極めなければならない時代であると再認識しなければなりません。